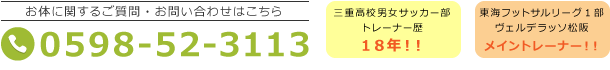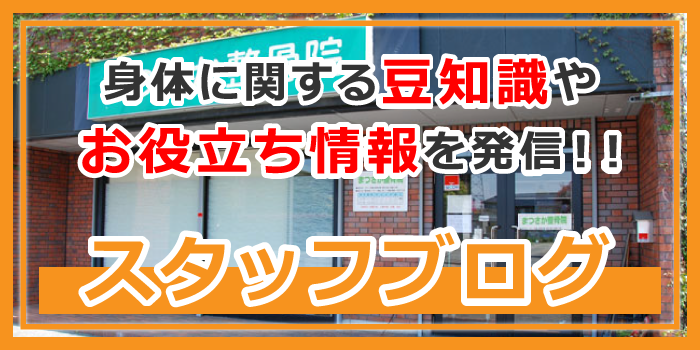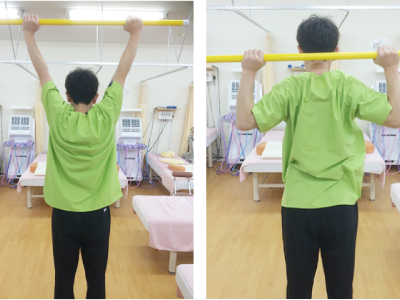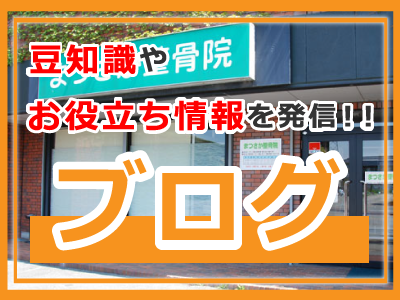バレーボールでの代表的なスポーツ障害や怪我
バレーボールは、相手の選手との接触による怪我は少ない反面、球への反応動作やアタックやトス、サーブといった球を打つ動作、特にジャンプやスライディング動作によるスポーツ障害や怪我が起こりやすく、膝や指を痛めることが多いです。
下記にバレーボール選手に多い怪我・スポーツ障害をご紹介いたします。
例1ジャンパー膝
ジャンプの際に痛みが出たり、階段の上り下りや走り込み時に痛みが出ます。ジャンプ動作の多い、バレーボールやバスケットボール、走り高跳びなどで跳躍を繰り返す方で膝下に痛みが出ている場合は、ジャンパー膝の可能性があります。ジャンプ動作はしない、マラソンランナーや他のスポーツ選手でも起こりえます。
症状と痛くなる場所
ジャンパー膝の症状と痛くなる場所は、膝のお皿の下に位置する膝蓋腱という箇所です。膝立ちした時に地面に当たる部分です。この膝蓋腱が炎症を起こすことで痛みが出ることから、ジャンパー膝の正式名称を「膝蓋腱炎」といいます。
原因
ジャンパー膝の原因は、「余計な血管が増えることに伴う神経繊維の増加によるもの」といわれています。腱が炎症を起こすと、血管が増えて傷ついた箇所を治そうとします。炎症が癒えれば、自然と増えた血管も減少するのですが、運動を休まずにいると、炎症箇所が癒えないまま、増えた血管が減らずに更に増える状態になります。血管の増加に伴い神経繊維も増加します。痛みの信号を脳に送る神経が増えるために、炎症に過敏になっていきます。
診断・予防・治療
ジャンパー膝の診断は、エコー検査で行えます。当院でも診断できますので、膝回りに痛みがある時はご相談ください。施術とジャンパー膝に効果的なストレッチや予防ストレッチ、テーピングの巻き方などの指導も行っています。軽傷であれば、数週間で治りますが、長期間練習をストップしても痛みが引かないなど重傷化してしまっている場合には、手術を含めた治療法を考える必要が出てきますので、専門の医療機関への受診が必要になることもあります。早期での対処が大切ですので、無理をせずに受診ください。
例2腰痛(腰椎分離症)
バレーボールに限らず、スポーツ選手では腰痛に悩まされている方が多くいます。腰は下半身と上半身を繋ぐ重要な箇所ですので、痛めてしまうとプレーに大きな影響を与え、日常生活にも支障が出てしまいます。バレーボールをしている方で腰痛が発症している場合の多くは、腰まわりの筋肉や筋膜の肉離れや使いすぎによる慢性疲労型腰痛と考えられます。急性のものは、ぎっくり腰や椎間板ヘルニアなどの可能性もありますし、腰痛がある場合はすぐに専門の医療機関や当院を受診してください。
腰椎分離症とは?
腰椎分離症とは、疲労骨折の一種で、背骨の後ろ側に亀裂が入っている状態のことです。スポーツなどで腰を捻る激しい運動を繰り返していると、細く衝撃に弱い部分が疲労骨折を起こして亀裂が入ることがあり、そのまま放置すると分離症に進展します。治療をしないで腰椎分離すべり症に進行すると大掛かりな手術になり、完治するまでの期間も長引きます。
初期治療をしっかり行うことで治すことは可能です。 成長期の大切な時期に発症しやすい疾患のため、早期発見と早期治療を行うことが肝要です。
腰椎分離症の原因
スポーツを活発に行っている10代の中高生に発症しやすく、骨が未発達な成長期に、激しい運動をしたり、繰り返し腰を捻る動作をすることが腰椎分離症の原因です。
野球、サッカー、バレーボール、バスケットボール、ラグビー、柔道など、身体の前後屈や腰のひねり、ジャンプからの着地といった動作を繰り返すスポーツの過度な練習が原因となるケースが多くみられます。 一般人の約5%、スポーツ選手では30〜40%が分離症を起こしているといわれています。疲労骨折でもあるため、骨が成長して正常な状態であれば腰椎分離症になるリスクは下がります。
やってはいけないこと
1 患部へのマッサージや指圧
痛みの強い時期から、腰を温めたり、無理に動かしたりマッサージを行ってはいけません。うつ伏せの状態でマッサージをしても余計に悪くなります。
2 無理して運動を続けない
痛みがある状態で今まで通りのスポーツを行ってはいけません。完治しませんし、日常生活に支障をきたすほど悪化します。
3 正しいやり方でしましょう
重いボール(ダイナマックス)を使って体をねじるトレーニングも、正しいやり方を理解せずに続けることはリスクになります。
予防
腰椎分離症になってしまうと最悪腰痛と付き合っていかなくてはならなくなるため、予防を心がけることをおすすめします。まずは10代の人は発症するリスクが高いため、腰を捻る動作を行うスポーツを行っているのであれば事前にストレッチを念入りにするようにしましょう。
また、腰回りの筋肉をつけることでも予防することができますが、筋トレで腰椎分離症になってしまうこともあるため、無理な筋トレは気を付ける必要があります。 詳細は院長が相談に乗りますので、腰に少しでも違和感を感じたら放置せず、来院されることをお奨めします。
例3捻挫
捻挫(ねんざ)とは、指や足首・手首といった関節をひねり傷める時に起こります。関節には大事な組織が多く集まっています。筋肉や腱、靭帯、関節包などの組織をひねった時に傷めてしまう症状を「捻挫」と呼んでいます。
バレーボールでは、特に足首の捻挫が多いですが、関節部分であればどこにでも起こりえます。
関節を構成している重要な組織である靭帯が、ひねった時に伸びたり切れてしまったり、ひどい症状の時には骨折してしまっていたということもあります。「ひねっただけだから」と捻挫を軽く考えず、痛みや腫れがあるなら早めの診断をおすすめいたします。
応急処置としては、RICE処置が有効です。無理に足首を回すストレッチなどはしないようにしましょう。
例4突き指
バレーボールでは突き指も多く起こりますが、突き指といっても、間接の脱臼、腱の断裂、靱帯の損傷など様々です。突き指は日常でも起こりますし、スポーツをしている方なら慣れてしまっているくらい頻繁に起こっています。安静にしていれば治るケースが多いですが、・変形している、・熱がある、・はれがある、・変色している、・痛みがひどい時は、病院で診てもらいましょう。
特に注意が必要なのが、ブロック時です。プロのバレーボール選手だと、アタッカーがブロックしている選手の小指を狙って突き指させにくることがあるかもしれません。また、アタックとブロックのタイミングがずれた時は、ブロッカーは指の力を緩めている状態で威力のある球が当たることで突き指をしやすくなります。
例5肩関節障害
バレーボール選手で肩に痛みが出る場合は、オーバーユースによるものが考えられます。肩に障害が起きやすい野球の投球動作と比べても、バレーボールは大きくて思いボールをアタックしたりサーブするわけですから酷使しがちになります。力いっぱいアタックする場合、動いていた筋肉や腱が打点の瞬間に反動で急激にストップします。
日常の動作では起きない不自然な酷使が、腱を摩耗し、肩の関節を安定させている腱板を損傷し痛みが出るのです。
ルーズショルダー(動揺性肩)
酷使により肩関節まわりの筋肉や靱帯による固定力が緩くなっている状態で、アタックやサーブすることで肩に痛みが出る症状です。もともと肩の関節が緩い方はなりやすく、予防にはインナーマッスルを鍛えたりストレッチが有効です。
肩関節反復性脱臼・亜脱臼・不安定症
肩は脱臼しやすい箇所です。身体の中でも腕は可動範囲が広く急激に動かせるため、肩の関節を構成する関節唇(かんせつしん)と靭帯といった箇所が損傷することで肩が外れたり、外れた感覚(亜脱臼)になったり、特定の方向への動きに不安定感が生じます。
肩の痛みは、プレーに大きな影響を与え、選手生命を脅かすこともあります。当院でのリハビリでは、・関節を締める、・姿勢や腕や肩の動かし肩の指導、・インナーマッスル強化などを行っていきます。重傷化するとリハビリの期間が長期化したり、手術が必要になることもありますので、早期に対処を心がけましょう。
例7シンスプリント
シンスプリントは、急な発進と急ブレーキを繰り返すスポーツでかかりやすく、バレーボール選手でも起こりえる障害です。
すねの骨の内側に鈍い痛みが生じます。症状が悪化すると、難治化し、プレーを長期的に休養する必要が出てきたり、手術が必要になる場合もあります。初期段階でのケアが重要です。どうしても出場したい試合がある場合などには、テーピング療法で患部へのストレスを軽減し、プレーを可能にすることも出来ますが、根本的な治療が大切な症状ですので、早期に病院または当院にて受診ください。
バレーボール選手の怪我や症例に経験豊富なまつさか整骨院
まつさか整骨院では、上記のような怪我をした場合、まずは病院(整形外科)にてレントゲン撮影と治療をおすすめしています。なぜなら、国家資格のある整骨院でも、レントゲンや外科手術は行うことはできず、精密な検査により治療やリハビリのプランを立てるためです。
ただし、本格的に競技をされているスポーツ選手の方の場合、病院とは別に当院でもご相談されることを強くおすすめいたします。特にそれがバレーボールのプレーによる運動機能障害である場合、ただ病院にかかるだけの場合と、当院も利用されるのでは試合復帰までにかかる時間と、復帰後の肉体的パフォーマンスに大きく差が出てしまいます。
病院は、もちろん治療に関しては専門家でありプロフェッショナルですが、「ただ、時間をかけて万全の状態に治す」、「怪我をする前にの状態に治す」のと、「復帰までのタイムスケジュールを計画して、怪我をする以前よりさらに良い結果を出すことを目的に、元の状態以上に治す」のとでは、選手の将来に大きな差が出てしまいます。
理由当院でスポーツ障害や怪我の治療を受ける5つのメリット
- 練習や試合復帰までをスケジュール化し早期回復をサポート。
- 怪我の予防策、回復トレーニングを徹底指導。
- 様々なスポーツに関する情報があるため、多様なプレー・トレーニングに関するアドバイス。
- ポジション別に怪我の原因を突き止め、正しいフォーム指導による再発防止・パフォーマンス向上。
- 症例によって、各種保険が適用できます。
例当院でのバレーボールの障害や怪我の症例
-
肘関節前方脱臼女子バレーボール部の高校2年生
練習で手押車していて、受傷。肘が痛みが出て、動かせなくなり、来院されました。
肘が後方に突き出て、ロックしていたため、肘関節前方脱臼の疑いがあると判断したため、スムーズな受診が出来るように、最寄りの整形外科に紹介状を書きました。
お母さんに肘の脱臼の内容説明「肘の周りの軟部組織の損傷があること」、「後遺症が出る可能性があること」、「脱臼が元に戻っても、しっかり固定するメリット」、をお話ししました。
整形外科でのレントゲン診断、処置の後に再度来院していただき、リハビリと再発しないようにフォームチェックや予防のためのストレッチ指導を行いました。